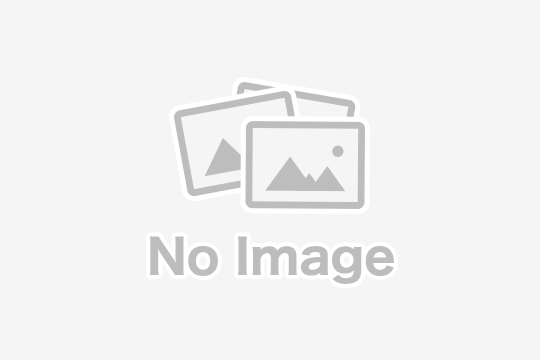「仕事中にアロマって使っていいのかな?」「職場で香りを使うと迷惑にならないか心配……」
このような不安を抱えながらも、集中力を高めたい、午後の眠気を解消したいと感じている方は多いのではないでしょうか。
職場でのアロマ活用は、周囲への配慮とルールを守れば、仕事の質を高める強力なツールになります。
この記事では、仕事場で安全かつマナーを守りながらアロマを使う方法を、シーン別のレシピとともにご紹介していきます。朝の始業から残業時、来客対応まで、あらゆる場面で役立つ香りの活用法をマスターしていきましょう!
職場でアロマを使う前に|香りマナーと安全の基本ルール

職場でアロマを使う際は、まず「香りのマナー」と「安全性」を理解しておくことが大切です。
なぜなら、香りは目に見えないからこそ、周囲への影響を見落としやすく、知らないうちに迷惑をかけてしまう可能性があるから。
ここでは、職場でアロマを使う前に必ず押さえておきたい基本ルールをお伝えしていきます。
香りは”職場共有空間”という意識を持とう
職場は自宅と違い、多様な価値観や体質を持つ人が集まる共有空間です。
したがって、「自分が好きな香り」が必ずしも全員にとって心地よいとは限りません。
香りの感じ方は人それぞれで、同じローズマリーでも「集中できる」と感じる人もいれば、「頭が痛くなる」と感じる人もいます。
実際、香りに対する感受性は個人差が大きく、体調や妊娠の有無によっても変わるもの。
このため、職場でアロマを使う際は常に「周囲と共有している空間である」という意識を持つことが重要です。
自分だけの空間ではないからこそ、控えめに、配慮しながら香りを取り入れていきましょう。
周囲への配慮と社内規定チェックのポイント
アロマを使い始める前に、必ず確認しておきたいのが社内規定と周囲の意見です。
企業によっては、香料の使用を制限している場合があります。
たとえば、食品工場や医療機関では香りの持ち込み自体がNGとされているケースも少なくありません。
まずは就業規則や社内ガイドラインに目を通し、アロマの使用が許可されているか確認してみてください。
加えて、同じデスク周辺にいる同僚に「アロマを使ってもいいか」を事前に尋ねることもマナーの一つです。
ちなみに、香りに敏感な人やアレルギー体質の人がいる場合は、無香料または極めて弱い香りにとどめることをおすすめします。
このように、ルールと人への配慮が揃って初めて、アロマは職場で安心して活用できるツールになるのです。
アロマを安全に使うための基本(希釈・滴数・火気・換気)
アロマオイル(精油)は濃縮された植物成分であり、原液のまま使うと肌トラブルや粘膜への刺激を引き起こす可能性があります。
そのため、必ず適切に希釈して使用しましょう。
ディフューザーで拡散する場合は、水や専用液に対して精油を数滴加える程度で十分です。
一般的には、6畳程度の空間で2〜3滴が目安。
さらに、火気の近くでオイルを扱わない、換気を定期的に行うといった基本も欠かせません。
というのも、精油は揮発性が高く、密閉空間で長時間使うと濃度が上がりすぎて、頭痛や吐き気を引き起こす恐れがあるからです。
香りを楽しむ時間は30分〜1時間程度にとどめ、その後は窓を開けて空気を入れ替えることが理想的。
安全に、そして快適にアロマを使うために、これらの基本ルールは必ず守っていきましょう!
アレルギー・妊娠・持病などへの配慮事項
職場には、さまざまな健康状態の方がいます。
たとえば、花粉症や喘息などのアレルギーを持つ人にとって、ユーカリやティーツリーといった精油が刺激になることもあります。
また、妊娠中の方には使用を避けるべき精油も存在するため、注意が必要です。
具体的には、ローズマリーやペパーミント、クラリセージなどは妊娠初期〜中期には控えたほうがよいとされています。
持病で薬を服用している方や、てんかんの既往歴がある方にも影響を及ぼす可能性がある精油があるため、事前に確認しておくと安心です。
ちなみに、香りに不安がある場合は使用を控えるか、医師や専門家に相談することをおすすめします。
このように、周囲の健康状態に配慮しながら香りを選ぶことが、職場での信頼と安全を守る第一歩です。
シーン別おすすめアロマレシピ|朝・会議前・昼食後・残業・来客対応

仕事中のシーンによって、求められる香りの効果は大きく変わります。
たとえば、朝にはシャキッと目覚める香りが欲しいですし、残業時には疲れを癒しながら集中できる香りが理想的です。
ここでは、仕事の各シーンに最適なアロマレシピを、具体的な滴数とともにご紹介していきます!
朝の始業前|集中スイッチを入れる柑橘×ハーブブレンド
朝は一日の始まりであり、頭をすっきりさせて集中モードに切り替えたいタイミングです。
そこでおすすめなのが、レモン2滴+ローズマリー1滴のブレンド。
レモンの爽やかさが気分を前向きにし、ローズマリーの清涼感が思考をクリアにしてくれます。
実際、柑橘系の香りは脳を活性化させる働きがあり、朝のスタートに最適だと言われています。
ディフューザーに水を張り、このブレンドを入れて始業の15分前から香らせておくと、デスクに着いた瞬間から集中力が高まるでしょう。
ちなみに、グレープフルーツやベルガモットに置き換えても、同様に爽やかなスタートを切れます。
朝のひと工夫で、一日のパフォーマンスが大きく変わってきますよ!
会議前・プレゼン前|緊張をほぐして自信を高める香り
会議やプレゼン前は、緊張で呼吸が浅くなったり、頭が真っ白になったりしがちです。
こうした場面には、ベルガモット2滴+フランキンセンス1滴のブレンドが効果的。
ベルガモットは不安を和らげ、心を落ち着かせる作用があり、フランキンセンスは深い呼吸を促して精神を安定させてくれます。
このブレンドをティッシュに垂らして、会議室に入る前に軽く香りを吸い込むだけでも、心拍が落ち着き、冷静さを取り戻せるでしょう。
さらに、ロールオンタイプのアロマに仕込んでおけば、手首や首筋にサッと塗って香りを纏うこともできます。
緊張をコントロールしながら、自信を持って臨める状態を作り出していきましょう!
昼食後・午後の眠気対策|頭をすっきりさせるブレンド
昼食後の眠気は、多くのビジネスパーソンが抱える悩みです。
なぜなら、食後は血糖値の変動により、どうしても集中力が落ちやすくなるから。
そこで活躍するのが、ペパーミント2滴+レモングラス1滴のブレンド。
ペパーミントの清涼感が眠気を吹き飛ばし、レモングラスの爽やかさが頭をシャープにしてくれます。
デスクに小型のアロマストーンを置いて、この組み合わせを垂らしておくと、午後の仕事もスムーズに進むはず。
また、ペパーミントはコーヒーとの相性もよいため、飲み物を楽しみながら香りを取り入れるのもおすすめです。
眠気に負けず、午後もしっかり集中力を保っていきましょう!
残業・締切前|集中力を保ちながら疲れを軽減する香り
残業や締切前は、体力的にも精神的にも疲れがピークに達しやすい時間帯です。
こうした状況では、ユーカリ2滴+ローズマリー1滴のブレンドが力を発揮します。
ユーカリはリフレッシュ効果が高く、疲労感を和らげる働きがあります。
一方、ローズマリーは記憶力や集中力をサポートしてくれるため、最後の追い込みにぴったり。
このブレンドをパーソナルインヘラー(携帯用アロマ吸入器)に仕込んでおけば、デスクで周囲に気兼ねなく香りを楽しめます。
さらに、30分ごとに軽くストレッチを挟みながら香りを嗅ぐと、心身ともにリセットされて作業効率も上がるでしょう。
疲れを感じたら無理せず、香りの力を借りて乗り切っていきましょう!
来客・打ち合わせ対応|印象を良くするウェルカムブレンド
来客時や打ち合わせでは、相手に好印象を与える香りを選ぶことが大切です。
オレンジスイート2滴+ティーツリー1滴のブレンドは、爽やかで清潔感があり、多くの人に受け入れられやすい組み合わせ。
オレンジスイートは親しみやすく温かい印象を与え、ティーツリーは空間を清潔に保つ抗菌作用も期待できます。
会議室や受付スペースでディフューザーを使う場合は、来客の15分前から香らせておくと、ちょうどよい香りの強さになります。
ただし、香りが強すぎると逆効果になるため、滴数は控えめに調整しましょう。
ちなみに、ラベンダーやゼラニウムを加えると、よりリラックスした雰囲気を演出できます。
第一印象を香りでさりげなくサポートしていきましょう!
香りの強さをコントロール|滴数・時間・距離で”ちょうどいい”香りに

アロマを職場で使う上で最も重要なのが、「香りの強さをコントロールすること」です。
というのも、香りが強すぎると周囲に不快感を与え、弱すぎると効果を感じられないから。
ここでは、滴数・時間・距離の3つの視点から、ちょうどよい香りに調整する方法をお伝えしていきます。
1滴=約0.05mL!滴数と空間サイズの目安表
精油1滴は、約0.05mL(ミリリットル)に相当します。
この量を基準に、空間のサイズに応じて適切な滴数を調整することが大切です。
たとえば、デスク周り(約1〜2畳)であれば1滴、個室や会議室(約6畳)なら2〜3滴が目安。
10畳以上の広いオフィススペースでは、4〜5滴程度まで増やしても問題ありません。
ただし、初めて使う精油の場合は、まず1滴から試して様子を見ることをおすすめします。
なぜなら、香りの強さは精油の種類によっても大きく異なるからです。
たとえば、ペパーミントやユーカリは少量でも強く香りますが、ラベンダーやフランキンセンスは穏やかに広がります。
このように、滴数と空間サイズのバランスを意識することで、快適な香りの環境を作り出せますよ!
香りを”オン・オフ”できる時間管理のコツ
香りは連続して嗅ぎ続けると、鼻が慣れてしまい効果を感じにくくなります。
これを「嗅覚疲労」と呼びますが、30分〜1時間ほどで起こることが一般的です。
そのため、アロマは「30分オン、30分オフ」のサイクルで使うことが理想的。
具体的には、ディフューザーをタイマー設定にしておくか、手動でオン・オフを切り替えながら使いましょう。
また、ティッシュ芳香法やアロマストーンであれば、香りが弱まったタイミングで引き出しにしまうだけで簡単にオフにできます。
ちなみに、長時間同じ香りを使い続けると、頭痛や吐き気を引き起こす可能性もあるため注意が必要です。
香りをオン・オフして、適度に休憩を挟みながら活用していきましょう!
残り香を防ぐ換気&布・紙への色移り対策
アロマを使った後、香りが残りすぎてしまうと、次に使う人や来客に不快感を与える恐れがあります。
そこで大切なのが、換気をしっかり行うことです。
使用後は窓を開けて5〜10分ほど空気を入れ替えると、残り香を効果的に取り除けます。
さらに、布製品(カーテンやクッション)に精油が付着すると、香りが長時間残りやすいため、直接触れないよう注意しましょう。
また、精油には色素が含まれているものもあり、紙や布に垂らすとシミになることがあります。
たとえば、オレンジやレモンなどの柑橘系は色移りしやすいため、ティッシュに垂らす際も白い部分に注意が必要です。
ちなみに、アロマストーンや専用のパッドを使えば、色移りの心配なく安心して香りを楽しめます。
このように、換気と色移り対策をセットで行うことで、快適な香り環境を維持していきましょう!
デスクでも迷惑にならない!拡散方法別アロマ活用ガイド

職場によっては、ディフューザーが使えない環境もあります。
しかし、香りを楽しむ方法はディフューザーだけではありません。
ここでは、デスク周りでも迷惑をかけずにアロマを活用できる、さまざまな拡散方法をご紹介していきます!
ティッシュ芳香法|最も簡単&すぐに止められる方法
ティッシュ芳香法は、アロマ初心者にも最適な手軽な方法です。
やり方は非常にシンプルで、ティッシュペーパーに精油を1〜2滴垂らし、デスクの隅やペンケースの近くに置いておくだけ。
香りが広がりすぎず、自分だけが楽しめる範囲に留まるため、周囲への配慮もしやすいのが特徴です。
また、香りが不要になったらティッシュをすぐに処分できるため、オン・オフのコントロールも簡単。
さらに、コストもほとんどかからず、特別な道具を用意する必要もありません。
ただし、精油をティッシュに垂らすと色移りすることがあるため、白いハンカチや布には使わないよう注意しましょう。
このように、ティッシュ芳香法は手軽さと安全性を兼ね備えた、職場向きの方法です!
アロマストーン・ロールオン|半径50cmの個人空間で香る
アロマストーンは、素焼きの陶器やセラミック製の小さな置物に精油を垂らして使うアイテムです。
香りがゆっくりと揮発するため、ディフューザーよりも穏やかに、半径50cm程度の範囲で香りを楽しめます。
デスクの上に置いても邪魔にならず、見た目もおしゃれなデザインが多いため、インテリアとしても活躍するでしょう。
一方、ロールオンタイプのアロマは、手首や首筋に直接塗って使える便利なアイテム。
香りを纏うように楽しめるため、周囲にほとんど影響を与えず、自分だけの香り空間を作れます。
ただし、肌に直接触れるため、必ず希釈済みのものを選び、パッチテストを行ってから使用してください。
ちなみに、ロールオンは持ち運びにも便利なので、外出先や移動中にも重宝します。
このように、個人空間で静かに香りを楽しみたい方には、アロマストーンやロールオンがぴったりです!
パーソナルインヘラー|周囲ゼロ干渉の集中ツール
パーソナルインヘラーは、鼻に近づけて直接香りを吸い込むタイプのアロマツールです。
形状はリップクリームに似ており、持ち運びやすく、周囲にまったく香りが広がらないのが最大の特徴。
使い方は簡単で、内部のコットンやフィルターに精油を数滴染み込ませ、必要なときに鼻を近づけて深呼吸するだけです。
たとえば、会議中や電話対応中に緊張を感じたとき、サッと取り出して香りを嗅げば、すぐにリフレッシュできます。
また、周囲に気づかれずに使えるため、「香りを使っていることを知られたくない」という方にも最適。
ちなみに、インヘラーは繰り返し使えるため、コストパフォーマンスも優れています。
集中力を高めたいとき、気分転換したいときに、自分だけの香りをいつでも楽しめる便利なアイテムです!
機器を使う場合の注意点とメンテナンス方法
ディフューザーなどの機器を使う場合は、定期的なメンテナンスが欠かせません。
なぜなら、精油の成分が機器内部に蓄積すると、雑菌やカビが繁殖し、香りが劣化したり健康被害を引き起こしたりする可能性があるからです。
使用後は毎回、水タンクを空にして乾燥させることが基本。
さらに、週に1回程度は、水とクエン酸またはアルコールで内部を洗浄しましょう。
また、超音波式ディフューザーの場合、振動板に汚れが溜まると霧の出が悪くなるため、綿棒で優しく拭き取ることをおすすめします。
加えて、使用する精油の種類によっては、タンクに色素や油分が残ることもあるため、こまめにチェックしてください。
ちなみに、メンテナンスを怠ると機器の寿命が短くなるだけでなく、香りの質も落ちてしまいます。
清潔に保つことで、長く快適にアロマを楽しんでいきましょう!
オフィス導入・運用ルールの作り方|香りゾーニングと社内掲示の工夫

オフィス全体でアロマを導入する場合、個人で使うときとは異なる配慮が必要です。
というのも、広い空間で複数の人が利用するため、ルールや使用エリアを明確にしなければ、トラブルの原因になりかねないからです。
ここでは、オフィスでアロマを安全かつ快適に運用するための具体的な方法をお伝えしていきます。
オフィス全体の”香りゾーニング”設計とは?
香りゾーニングとは、オフィス内で「香りを使ってよいエリア」と「使わないエリア」を明確に区分けすることです。
たとえば、休憩スペースや会議室では香りを取り入れ、執務エリアや食事スペースでは使用を控えるといった分け方が考えられます。
なぜこうした区分けが必要かといえば、全員が香りを心地よく感じるわけではないからです。
実際、香りに敏感な人やアレルギーを持つ人がいる場合、執務エリア全体に香りが広がると、体調不良を訴える可能性があります。
そのため、香りを使うエリアを限定し、そこに近づかなければ影響を受けない環境を作ることが重要です。
ちなみに、ゾーニング設計を行う際は、社員へのアンケートを実施して意見を集めると、より納得感のあるルールが作れます。
全員が快適に過ごせるオフィス環境を目指していきましょう!
使用エリア別の注意点(会議室/受付/休憩スペース)
香りを使うエリアごとに、適切な使い方や注意点があります。
まず、会議室では来客や打ち合わせの前後に香りを使うことが一般的です。
ただし、長時間の会議では香りが強すぎると集中の妨げになるため、使用時間は15〜30分程度に留めましょう。
また、会議終了後は必ず換気を行い、次の利用者に香りが残らないよう配慮してください。
次に、受付スペースでは、来客に好印象を与える穏やかな香りが理想的です。
オレンジスイートやラベンダーなど、万人受けする香りを選び、香りの強さは控えめに設定しましょう。
休憩スペースでは、リラックス効果のある香りを使うことで、社員のストレス軽減や気分転換をサポートできます。
ただし、食事をとる場所では香りが食事の味や匂いに影響するため、使用を避けたほうが無難です。
このように、エリアごとの特性を理解して香りを使い分けていきましょう!
社内掲示テンプレートとルール策定のヒント
オフィスでアロマを導入する際は、社内掲示やガイドラインを作成しておくと、トラブルを未然に防げます。
たとえば、「アロマ使用エリアのお知らせ」として、使用可能な場所・時間帯・使用するオイルの種類を明記しておくと分かりやすいでしょう。
また、「香りに不快感を感じた場合は、総務部までご連絡ください」といった相談窓口を設けておくことも大切です。
さらに、掲示には「使用する精油は天然由来のもので、安全性に配慮しています」といった安心感を与える文言を加えると、社員の理解を得やすくなります。
ちなみに、ルール策定の際は、社員代表や衛生管理者を交えて議論すると、より実効性の高いルールが作れます。
掲示物のデザインも親しみやすくすることで、社員が自然にルールを守りやすくなるでしょう。
明確なルールと丁寧な周知が、快適なアロマ環境を支えていきます!
トラブルを防ぐ報告・相談フローの整備
どれだけ配慮していても、香りに関するトラブルはゼロにはできません。
そのため、万が一のときに備えて、報告・相談フローを整備しておくことが重要です。
たとえば、「香りが強すぎる」「体調が悪くなった」といった声があった場合、どこに連絡すればよいかを明確にしておきましょう。
総務部や人事部を窓口にして、匿名でも相談できる仕組みを作っておくと、社員が声を上げやすくなります。
また、相談を受けた際は、すぐに対応することが大切です。
具体的には、香りの使用を一時停止したり、使用エリアを見直したりといった柔軟な対応が求められます。
ちなみに、相談内容を記録しておくことで、今後のルール改善に役立てることもできます。
このように、トラブルを防ぐ仕組みと対応の流れを整えることで、安心してアロマを導入できる環境が整います!
季節・体調別アロマ応用レシピ|一年中快適に香りを楽しむ方法

アロマの魅力は、季節や体調に合わせて香りを変えられることです。
というのも、春には花粉症対策、夏には湿気やニオイ対策、冬には風邪予防といったように、季節ごとに求められる効果が異なるからです。
ここでは、一年を通じて快適に香りを楽しむための応用レシピをご紹介していきます!
春(花粉・新生活ストレス)におすすめのブレンド
春は新生活がスタートする季節であり、期待と同時にストレスも感じやすい時期です。
さらに、花粉症に悩まされる方も多く、鼻づまりや目のかゆみで集中力が削がれることも少なくありません。
そこでおすすめなのが、ユーカリ2滴+ペパーミント1滴+ラベンダー1滴のブレンドです。
ユーカリは鼻通りをよくし、ペパーミントが爽快感を与え、ラベンダーがストレスを和らげてくれます。
実際、ユーカリには抗炎症作用があり、花粉症の不快な症状を軽減する効果が期待できると言われています。
ティッシュに垂らして鼻の近くで軽く吸い込むと、呼吸が楽になり、気分もすっきりするでしょう。
また、新生活の緊張感を和らげたい場合は、ベルガモット2滴+フランキンセンス1滴の組み合わせも効果的。
春特有の不安定な心と体を、香りの力でサポートしていきましょう!
梅雨・夏(湿気・ニオイ対策)におすすめのブレンド
梅雨から夏にかけては、湿気とニオイが気になる季節です。
オフィスでも、エアコンの使用頻度が増える一方で、窓を開けにくくなり、空気がこもりがちになります。
こうした環境には、ティーツリー2滴+レモン2滴のブレンドが最適。
ティーツリーは抗菌・抗ウイルス作用が高く、空気を清潔に保つ効果があります。
一方、レモンの爽やかな香りは、ジメジメした空気を一掃し、気分をリフレッシュさせてくれます。
さらに、ペパーミント1滴を加えると、清涼感が増して暑さ対策にもなるでしょう。
ちなみに、夏場は汗のニオイが気になることもありますが、香りで無理に隠そうとすると逆効果になることがあります。
そのため、香りはあくまで空間の清潔感を保つ目的で使い、体臭対策は別途行うことをおすすめします。
湿気と暑さに負けず、快適なオフィス環境を整えていきましょう!
秋(集中・気分の落ち込みケア)におすすめのブレンド
秋は気温が下がり始め、日照時間も短くなるため、気分が落ち込みやすい季節です。
いわゆる「季節性の気分の落ち込み」を感じる方も多く、仕事への意欲が湧きにくくなることがあります。
こうしたときには、オレンジスイート2滴+ローズマリー1滴+ゼラニウム1滴のブレンドがおすすめ。
オレンジスイートは明るく温かい気持ちを引き出し、ローズマリーが集中力をサポートします。
そして、ゼラニウムは気持ちのバランスを整え、穏やかな安定感をもたらしてくれます。
実際、秋は「実りの季節」でありながら、心身ともに疲れが出やすい時期でもあります。
そのため、リフレッシュとリラックスのバランスを取りながら、無理なく集中できる環境を作ることが大切です。
ちなみに、読書の秋にちなんで、フランキンセンスを加えると深い思考を促す効果も期待できます。
秋の静かな空気の中で、香りとともに集中力を高めていきましょう!
冬(乾燥・風邪予防・リラックス)におすすめのブレンド
冬は乾燥が気になり、風邪やインフルエンザが流行しやすい季節です。
オフィスでも、暖房による乾燥で喉を痛めたり、体調を崩したりする人が増えます。
こうした時期には、ティーツリー2滴+ユーカリ1滴+ラベンダー1滴のブレンドが効果的。
ティーツリーとユーカリは抗菌・抗ウイルス作用があり、空気中のウイルス対策に役立ちます。
また、ラベンダーはリラックス効果があり、年末の忙しさで高まったストレスを和らげてくれるでしょう。
さらに、冬の夜は日が短く、帰宅後もなかなかリラックスできないという方も多いはず。
そんなときは、オレンジスイート2滴+シナモン1滴(または少量)のブレンドで、温かみのある香りを楽しむのもおすすめです。
ただし、シナモンは刺激が強いため、使用量には十分注意してください。
冬の寒さと乾燥に負けず、香りで体調管理をサポートしていきましょう!
体調や気分別の”1滴チェンジ”応用テク
アロマの面白さは、たった1滴変えるだけで、香りの印象や効果がガラリと変わることです。
たとえば、「集中したいけど少しリラックスもしたい」という場合、ローズマリー2滴にラベンダー1滴を足すだけで、バランスの取れた香りになります。
また、「頭痛がするけど眠気も取りたい」というときは、ペパーミント1滴+ラベンダー1滴の組み合わせが有効。
ペパーミントが頭痛を和らげ、ラベンダーが緊張をほぐしてくれます。
このように、体調や気分に応じて1滴を変えるだけで、自分にぴったりの香りを作り出せるのです。
さらに、香りのブレンドに慣れてきたら、3種類以上の精油を組み合わせて、オリジナルレシピを作るのも楽しいでしょう。
ちなみに、記録をつけておくと、「このブレンドは集中できた」「この組み合わせはリラックスできた」といった振り返りができ、より自分に合った香りを見つけられます。
体調や気分の変化に合わせて、香りを自由に調整していきましょう!
まとめ

仕事場でアロマを取り入れる際は、周囲への配慮と安全なルールを守ることが何よりも大切です。
香りは目に見えないからこそ、滴数や使用時間、換気といった基本をしっかり押さえることで、迷惑をかけずに快適な環境を作り出せます。
また、朝の始業前、会議前、昼食後、残業時、来客対応といったシーン別に香りを使い分けることで、仕事のパフォーマンスを最大限に引き出すことができるでしょう。
さらに、季節や体調に応じてブレンドを変えることで、一年中アロマの恩恵を受けられます。
ティッシュ芳香法やアロマストーン、パーソナルインヘラーなど、ディフューザーを使わない方法もあるため、職場の環境に合わせて柔軟に選んでみてください。
今回ご紹介したレシピや方法を参考に、ぜひあなたの仕事場にも香りを取り入れてみることをおすすめします。
快適な香りとともに、充実した仕事時間を過ごしていきましょう!